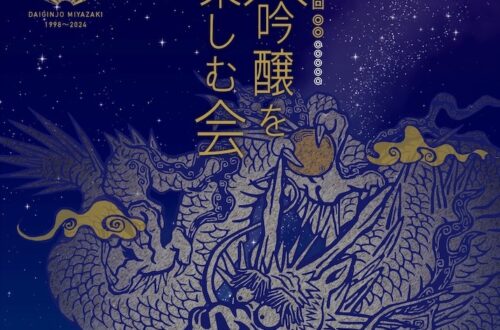山奥の小さな酒蔵・獺祭
新幹線で博多から50分
徳山駅で降り車で岩国方面に獺祭の蔵へ向かう
30分ほどドライブするとそこから山の方へ曲がる
何回かカーブを曲がり、山の中に進んでいくと
トータル40分ほどで突然獺祭の蔵が見えてくる
桜井博志社長がにこやかな笑顔で迎えてくれた
人口は300人ほどの小さな町だが
獺祭に勤める人だけでも100人以上と言うから獺祭町と言っても良いぐらい
山奥だから一番困るのは駐車場だと社長は嘆く
さて工場見学へ
第2蔵の4階に案内される
ここは少量ずつの米の洗いと水に浸す作業を
手際よく手作業で3~4人で行っている
水温や米糠の具合や水に浸す秒単位の時間までを
細かい作業を徹底している
3階に降りるとタンクがびっしり
すべてが大変綺麗でタンクの中の温度も一目瞭然でわかる
一番高いのは2週間程度の発行を行ったタンクで12度ぐらい
そのほかはほぼ4度ぐらいだった
出来てから2日目、10日目、20日目、28日目などを見せてもらい
発酵の移り変わりを見ることができた
この蔵で一番驚くのが第一蔵にある麹室だろう
麹室はほぼすべてが杉だが
天井も壁もステンレス張りと言う今までに見たこともない型破りの室だ
なぜこのシステムにしたのか?
桜井社長は杉板は勝手に湿度を調整してくれるが
天井からダクトを通し手管理した方が制御できると考えた
またステンレスだと細菌汚染などの心配も抑えられると!
酒がどれだけ造れるかは麹室で決まるともおっしゃっていた
誰も作ったことがない麹室の工事は引き受け手がいなく
地元の空調業者にお願いした
話題の遠心分離器も見せていただいた
通常の絞りで作るよりもできる量は12分の一の少なさ
しかし品質の良い酒ができるために
この遠心分離機を使っている
2号機はこれより小型になったと・・・・
今日本で一番忙しい蔵元のおひとりだと言っても良いだろう
桜井社長に建築中の蔵についてお聞きする
今建築中なのは第3蔵
12階までの高さになると言う
事務所も販売所もこの中に入りきれると思ったが・・・
酒造りのことを一番に考えると
無理になったと笑顔で答えてくれた
試飲と販売の場所では一人1本までお酒を売っている
ここでしかかえない試と言うお酒を買ってみる
磨き2割3分で使えなかったお米で醸されているらしい
味が楽しみである
またお酒の本がたくさん置いてあるのも嬉しい
時間があればゆっくり読書の時間も楽しいだろう
先代の父親と意見が合わず飛び出して石材業を興した桜井社長
その先代の急死で後を継ぎ
苦境にあえぐ蔵を建て直し
大吟醸の獺祭ブランドを全国をはじめ世界に広げつつある
山奥の町の故郷をいつまでも大切にして
本拠地を山奥から移さない獺祭の心意気
地方から生まれた資源の活性化
そのお手本と言うべきブランドの酒だ
私もその心を少し習いたいと思ってしまった!